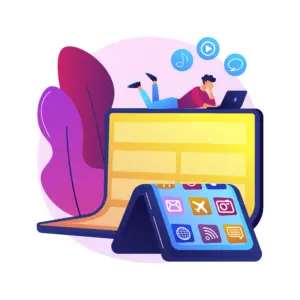ナレッジハブ
2025/9/24
SEOで検索上位を独占!集客力アップを実現する実践ノウハウ
今日のデジタル社会において、ビジネスの成長は、いかにしてオンライン上で見込み客に見つけてもらえるかに懸かっています。その最も強力な手段が、SEO(検索エンジン最適化)です。しかし、GoogleのアルゴリズムがAIを駆使して日々進化を続ける今、「キーワードを詰め込む」「とにかく記事を量産する」といった旧来の常識はもはや通用しません。2025年以降のSEOで求められるのは、ユーザーの検索意図を深く洞察し、競合を凌駕する価値を提供し、技術的な健全性を保ち続けるという、包括的かつ戦略的なアプローチです。本稿では、単なるテクニックの紹介に留まらず、検索上位を独占し、持続的な集客力アップを実現するための、今日から実践できる具体的なノウハウを、最新のトレンドを交えながら網羅的に解説します。このノウハウを手に、あなたのビジネスを新たなステージへと引き上げましょう。
目次
1. SEOとは何か?検索エンジンの評価基準を理解する
SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)とは、GoogleやYahoo!といった検索エンジンにおいて、ユーザーが特定のキーワードで検索した際に、自社のWebサイトをできるだけ上位に表示させるための一連の取り組みの総称です。なぜ上位表示が重要なのか。それは、現代の消費者が商品やサービスを探す際の最初の行動が「検索」であり、検索結果の1ページ目、特に上位に表示されるサイトが、アクセスの大部分を獲得するという紛れもない事実があるからです。
このSEOというゲームのルールメーカーであるGoogleの「評価基準」を正しく理解することこそ、全ての施策の出発点となります。
Googleの使命:ユーザーファーストの徹底
Googleが掲げる最大の使命は、「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること」です。この使命を検索エンジンに当てはめると、「ユーザーの検索クエリ(質問)に対して、最も的確で、最も有益で、最も信頼できる答えを、最も速く提供すること」と言い換えられます。
SEOの本質は、Googleのアルゴリズムの穴を突くことではありません。Googleと同じ方向、すなわち「ユーザー」の方向を向き、徹底的にユーザーにとっての価値を追求すること。この「ユーザーファースト」という基本理念を理解することが、アルゴリズムの変動に左右されない、本質的なSEOの第一歩です。
検索順位を決める3つの柱
Googleは、200以上もの評価項目を複雑に組み合わせて検索順位を決定していると言われていますが、その根幹は、大きく分けて以下の3つの柱で構成されています。
- コンテンツ (Content):
- 評価基準: そのページに、ユーザーが検索したキーワードの意図(インテント)を満たす、質の高い情報が、網羅的に含まれているか。
- 解説: これが最も重要な要素です。例えば「SEO 対策」と検索したユーザーは、SEOの具体的な方法を知りたいはずです。その問いに対し、網羅的で、分かりやすく、そして信頼できる答えを提供しているページが、コンテンツの質が高いと評価されます。
- オーソリティ (Authority) / 信頼性:
- 評価基準: そのWebサイトやコンテンツの作成者が、そのトピックにおいてどれだけ信頼でき、権威があると見なされているか。
- 解説: Googleは、第三者からの評価を重視します。その最も代表的な指標が、他のWebサイトからのリンク、すなわち「被リンク(バックリンク)」です。質の高い、関連性の高いサイトから多くリンクされているサイトは、「多くの専門家から推薦されている信頼できるサイト」として、権威性が高いと評価されます。
- テクニカル (Technical) / ユーザビリティ:
- 評価基準: 検索エンジンのクローラー(情報を収集するロボット)が、サイトの情報を正しく、そして効率的に認識できるか。また、ユーザーがサイトを快適に利用できるか。
- 解説: サイトの表示速度、スマートフォンでの見やすさ(モバイルフレンドリー)、サイト構造の分かりやすさ、セキュリティ(SSL化)などが含まれます。どれだけ良いコンテンツがあっても、サイトの技術的な基盤が脆弱では、その価値は正しく評価されません。
E-E-A-T:コンテンツ品質評価の核心
Googleがコンテンツの質を評価する上で、特に重視しているのが「E-E-A-T」という基準です。これは、Googleの検索品質評価ガイドラインで定められている、良質なサイトの条件です。
- E – Experience (経験): コンテンツの作成者が、そのトピックについて直接的な経験を持っているか。
- E – Expertise (専門性): コンテンツの作成者が、そのトピックの専門家であるか。
- A – Authoritativeness (権威性): コンテンツの作成者やサイトが、そのトピックの権威として認知されているか。
- T – Trustworthiness (信頼性): サイト全体が信頼できる情報源であるか。
例えば、医療に関する情報であれば、医師が自らの臨床経験に基づいて執筆・監修した記事は、E-E-A-Tが非常に高いと評価されます。自社のビジネスにおいても、「自社だからこそ語れる経験」「業界の専門家としての知見」をコンテンツに反映させることが、SEO成功の鍵となります。
SEOとは、単なる技術的な作業ではなく、自社の専門性を棚卸しし、それを顧客の言葉で、最高の形で提供していく、事業活動そのものと深く結びついた、戦略的な取り組みなのです。
2. 顧客が検索するキーワードを網羅する方法
効果的なSEO戦略は、顧客がどのような言葉(キーワード)で、何を求めて検索しているのかを、深く、そして網羅的に理解することから始まります。企業側が考えている製品名や専門用語と、顧客が実際に検索窓に打ち込む言葉の間には、しばしば大きなギャップが存在します。このギャップを埋め、顧客の思考に寄り添ったキーワードを網羅的に発掘・整理することが、集客機会を最大化するための羅針盤となります。
検索意図(インテント)のマッピング
キーワード調査の核心は、単語をリストアップすることではなく、その背後にある「検索意図(インテント)」を読み解き、整理することです。検索意図は、顧客の購買プロセスにおける段階と密接に関連しています。
- 情報収集段階 (Informational Intent):
- 意図: 何かを知りたい、学びたい、課題を認識した段階。
- キーワード例: 「〇〇 とは」「△△ 方法」「□□ 原因」
- アプローチ: 課題解決のためのハウツー記事、用語解説、ガイドなどのコンテンツでアプローチします。
- 比較検討段階 (Commercial Investigation):
- 意図: 複数の選択肢を比較し、どれが自分に最適かを見極めたい段階。
- キーワード例: 「〇〇 △△ 比較」「□□ おすすめ」「〇〇 口コミ」
- アプローチ: 比較記事、ランキング、レビュー、導入事例などのコンテンツで、自社の優位性を示します。
- 購買段階 (Transactional Intent):
- 意図: 購入や申し込みを決意しており、具体的な行動を起こす段階。
- キーワード例: 「〇〇 購入」「△△ 料金」「□□ 問い合わせ」「地域名 〇〇」
- アプローチ: サービスページ、料金ページ、問い合わせフォームなどを最適化し、スムーズな行動を促します。
これらの検索意図を軸に、顧客がどのような思考の旅(カスタマージャーニー)を辿るかを想像し、各段階で検索されうるキーワードをマッピングしていくことが、戦略的なキーワード調査の第一歩です。
キーワードを網羅的に発掘する4ステップ
ステップ1:軸となるキーワード(シードキーワード)の洗い出し
まず、自社のビジネスの核となる、最も基本的で重要なキーワードをブレインストーミングで洗い出します。
- 自社のサービス・商品名: 例:「会計ソフトfreee」
- サービス・商品のカテゴリ: 例:「会計ソフト」「確定申告 クラウド」
- 顧客の課題・ニーズ: 例:「経理 効率化」「請求書 作成」
ステップ2:キーワードリサーチツールによる拡張
シードキーワードを元に、専用のツールを使って関連キーワードを網羅的に収集・拡張します。
- Googleキーワードプランナー: Google広告の無料ツール。キーワードの月間検索ボリュームや、関連キーワードの候補を大量に取得できます。SEOのキーワード調査における基本中の基本です。
- ラッコキーワード: 無料で利用できる高機能ツール。Googleサジェスト(検索候補)、関連Q&A(Yahoo!知恵袋など)、関連ハッシュタグなどを一括で取得でき、ユーザーの具体的な疑問や関心事を把握するのに非常に役立ちます。
- Ahrefs (エイチレフス) / SEMrush (セムラッシュ): 有料のプロ向けツール。自社の調査だけでなく、競合サイトがどのようなキーワードで流入を獲得しているかを丸裸にできます。競合が獲得していて、自社が対策できていない「お宝キーワード」を発見する上で絶大な威力を発揮します。
ステップ3:ロングテールキーワードへの深掘り
キーワードには、検索ボリュームが大きく競合も激しい「ビッグキーワード」(例:「会計ソフト」)と、2語、3語以上の組み合わせで、検索ボリュームは小さいが検索意図が非常に具体的な「ロングテールキーワード」(例:「個人事業主 確定申告 会計ソフト おすすめ」)があります。
SEOで成果を出すためには、このロングテールキーワードをいかに網羅できるかが鍵となります。ロングテールキーワードは、意図が明確なためコンバージョン率が高く、競合も比較的少ないため、着実に上位表示を狙えるからです。
ステップ4:キーワードのグルーピングとマッピング
収集した数百、数千のキーワードを、検索意図が近いもの同士でグルーピング(分類)します。
- 例: 「会計ソフト 使い方」「会計ソフト 初心者」「会計ソフト 入力方法」は、「使い方を知りたい」という同じ意図を持つグループです。
- このグループに対して、「1つのコンテンツ(1ページ)」を割り当てます。つまり、「初心者向け会計ソフトの使い方完全ガイド」のような1つの記事で、このグループのキーワード群の検索意図をまとめて満たすことを目指します。
この地道なグルーピングとマッピング作業が、サイト全体の情報構造を論理的に設計し、ユーザーと検索エンジンの両方にとって分かりやすいサイトを構築するための、最も重要な設計図となるのです。
3. 競合に打ち勝つSEOコンテンツ戦略
キーワード調査によって「戦うべき市場」が明確になったら、次はその市場で「いかにして競合に打ち勝ち、顧客に選ばれるか」を決定づける、コンテンツ戦略を策定します。現代のSEOにおいて、コンテンツは「王様」です。しかし、ただ闇雲に質の高い記事を作成するだけでは、すでに上位を独占している強力な競合に勝つことはできません。
競合を徹底的に分析し、彼らが満たしきれていない「ギャップ(隙間)」を見つけ出し、そこに自社ならではの「独自価値」を投入する。この戦略的思考こそが、後発でも上位表示を実現するための鍵となります。
競合分析:敵を知り、己を知る
まず、ターゲットとするキーワードで上位表示されている上位10サイトのコンテンツを、徹底的に分析します。彼らは、Googleが「現時点でのベストアンサー」と認めている、いわば模範解答です。
- コンテンツ・ギャップ分析:
- トピックの網羅性: 上位サイトが共通して扱っているトピック(見出し)は何かをリストアップします。これらは、ユーザーの検索意図を満たす上で「必須の要素」です。自社のコンテンツに、これらの必須要素が漏れていないかを確認します。
- コンテンツの切り口・フォーマット: テキストだけでなく、図解、動画、比較表、Q&Aなど、どのようなフォーマットで情報を伝えているか。どのような切り口(初心者向け、専門家向けなど)で解説しているかを分析します。
- 競合の弱点(ギャップ)を探す:
- 「このトピックについて、どのサイトも表面的な解説しかしていないな」
- 「情報が少し古くなっているな」
- 「専門的すぎて、初心者には分かりにくいな」
- 「具体的な事例やデータが不足しているな」
- この「競合が満たしきれていないユーザーの潜在的なニーズ」こそが、自社が勝負をかけるべき一点です。
「10x Content」の思想:10倍の価値を提供する
競合の弱点を見つけたら、「競合サイトよりも10倍優れたコンテンツを作る」という思想(10x Content)で、コンテンツを企画します。単に情報を付け足すだけでなく、あらゆる側面で競合を凌駕することを目指します。
- 網羅性で勝つ: 競合が扱っているトピックをすべて含んだ上で、彼らが見落としているトピックを追加し、圧倒的な情報量と網羅性を実現します。「この記事一本を読めば、このテーマについてはすべてが分かる」という状態を目指します。
- 分かりやすさで勝つ: 専門的な内容を、独自の図解やイラスト、比喩を多用して、どこよりも分かりやすく解説します。
- 独自性・信頼性で勝つ (E-E-A-T):
- 競合が提供していない、自社ならではの一次情報を盛り込みます。
- 独自の調査データやアンケート結果 (Experience, Expertise)
- 顧客へのインタビューに基づいた具体的な導入事例 (Experience)
- 自社の専門家による、実務経験に基づいた見解やアドバイス (Expertise)
- 専門家(社外でも可)による記事の監修 (Authoritativeness, Trustworthiness)
- この「自社にしか書けない情報」こそが、競合との絶対的な差別化要因となり、E-E-A-T評価を高める上で最も重要です。
- 競合が提供していない、自社ならではの一次情報を盛り込みます。
トピッククラスターモデル:サイト全体の専門性を示す
個々の記事の質を高めるだけでなく、それらの記事を戦略的な内部リンクで結びつけ、サイト全体として特定のテーマに関する専門性(トピックオーソリティ)をGoogleに示す手法が「トピッククラスターモデル」です。
- 構造:
- ピラーページ: ある広範なトピック(例:「コンテンツマーケティング」)について、網羅的に解説した「柱」となるページ。ビッグキーワードでの上位表示を目指します。
- クラスターページ: ピラーページで扱った個別のサブトピック(例:「記事構成 作り方」「SEOライティング」「効果測定 KPI」)について、それぞれを深く掘り下げた詳細なページ。ロングテールキーワードでの上位表示を目指します。
- 内部リンク: 各クラスターページから、中心となるピラーページへとリンクを張ります。また、ピラーページからも、各クラスターページへとリンクを張ります。
- 効果:
- この構造により、各ページが孤立せず、テーマごとに関連性の強いコンテンツ群としてまとまります。
- Googleは、このリンク構造を通じて、「このサイトは、”コンテンツマーケティング”というテーマについて、非常に体系的で、専門性の高い情報を持っている」と認識し、サイト全体の評価(トピックオーソリティ)を高めます。
- 結果として、個々のクラスターページだけでなく、競合の激しいピラーページの順位上昇にも繋がります。
競合に打ち勝つSEOコンテンツ戦略とは、個々の記事で「10倍の価値」を提供し、それらをトピッククラスターモデルで繋ぎ合わせることで、特定のテーマにおける絶対的な第一人者としての地位を、Webサイト上で確立していく、壮大かつ緻密な知的労働なのです。
4. サイトエラーをなくすテクニカルSEOのチェックリスト
どれだけ高品質なコンテンツを用意し、優れた被リンク戦略を実行しても、Webサイトという「土台」そのものに技術的な欠陥があれば、その努力は水泡に帰してしまいます。テクニカルSEOとは、Webサイトを検索エンジンのクローラー(情報を収集するロボット)にとって巡回しやすく、かつ内容を正しく理解できる状態に整備し、さらにユーザーにとっても快適に利用できる環境を整えるための一連の技術的な施策です。
ここでは、サイトの評価を損なう致命的なエラーを防ぎ、SEOの成果を最大化するために、定期的にチェックすべきテクニカルSEOの項目をリスト形式で解説します。
クローラビリティ(巡回しやすさ)のチェックリスト
クローラーがサイト内のページをスムーズに発見し、巡回できるかを確認します。
- □ XMLサイトマップは設置・送信されているか?:
- サイト内の全ページの地図である「XMLサイトマップ」を作成し、サーバーにアップロードします。
- Googleサーチコンソールに登録し、正しく送信されていることを確認します。新しいページを追加したら、サイトマップも更新されるように設定します。
- □ robots.txtは正しく設定されているか?:
- クローラーのアクセスを制御する「robots.txt」ファイルで、重要なページへのアクセスを誤ってブロック(Disallow)していないかを確認します。
- □ サイト内に孤立したページ(オーファンページ)はないか?:
- サイト内のどのページからもリンクされていないページは、クローラーに発見されにくくなります。全てのページが、少なくとも1つ以上の内部リンクで辿れる状態になっているかを確認します。
- □ 内部リンクは適切に設置されているか?:
- 関連性の高いページ同士が、分かりやすいアンカーテキストでリンクされているか。
- 重要なページには、多くの内部リンクが集まるような構造になっているか。
- パンくずリストは設置されているか。
- □ サイトの表示速度は遅くないか?:
- 表示速度の遅さは、ユーザー体験を損なうだけでなく、クローラーが時間内に巡回できるページ数を減らしてしまいます。PageSpeed Insightsなどのツールで定期的にチェックします。
インデクサビリティ(理解しやすさ)のチェックリスト
クローラーが収集した情報を、検索エンジンが正しく解釈し、インデックス(データベースへの登録)できるかを確認します。
- □ titleタグは各ページでユニークかつ最適化されているか?:
- 全ページで、内容を的確に表す、ユニークなtitleタグが設定されているか。
- ターゲットキーワードを含み、30文字程度で簡潔に記述されているか。
- □ meta descriptionは設定されているか?:
- 検索結果のスニペット(説明文)に表示されるmeta descriptionが、クリックを促す魅力的な内容で、各ページごとに設定されているか。(120文字程度が目安)
- □ h1タグは各ページに1つだけ設定されているか?:
- ページの大見出しであるh1タグが、各ページに1つだけ、そのページの内容を要約する形で使用されているか。
- □ URLの重複(重複コンテンツ)は発生していないか?:
- wwwの有無、index.htmlの有無、httpと`https- □ 画像は最適化されているか?:
- 全ての画像に、その画像の内容を説明するalt属性が設定されているか。
- ファイルサイズが大きすぎないか。WebPなどの次世代フォーマットを利用しているか。
ユーザビリティとセキュリティのチェックリスト
ユーザーと検索エンジンの両方からの信頼性を確保します。
- □ サイトは常時SSL化(HTTPS)されているか?:
- 全ページがhttps://で始まるURLになっているか。httpでアクセスした場合、httpsに正しくリダイレクトされるか。
- □ モバイルフレンドリーに対応しているか?:
- スマートフォンで閲覧した際に、レイアウトが崩れず、テキストやボタンが適切に表示されるか(レスポンシブデザイン)。Googleのモバイルフレンドリーテストで確認します。
- □ 404エラー(リンク切れ)ページは放置されていないか?:
- Googleサーチコンソールの「カバレッジ」レポートなどで、存在しないページへのリンク(404エラー)がないかを確認します。もし存在する場合、適切なページへの301リダイレクトを設定するか、リンクを修正します。
- □ 構造化データは正しく実装されているか?:
- パンくずリスト、記事、FAQ、ローカルビジネス情報などに、適切な構造化データを実装することで、検索エンジンが内容をより深く理解し、リッチリザルトとして表示される可能性が高まります。Googleのリッチリザルトテストで、エラーなく認識されるかを確認します。
これらの項目は、Googleサーチコンソールを活用することで、その多くを無料でチェックできます。月に一度、あるいは四半期に一度でも、このチェックリストに沿ってサイトの「健康診断」を行う習慣をつけることが、SEOの成果を安定させるための、縁の下の力持ちとなるのです。
5. 影響力の高い被リンクを獲得するテクニック
SEOの評価基準において、コンテンツの質と並んで、サイトの権威性(Authoritativeness)を測る上で今なお絶大な影響力を持つのが「被リンク(バックリンク)」です。Googleは、外部のWebサイトから自サイトに向けられたリンクを、そのサイトに対する「信頼の投票」と見なします。特に、権威あるサイトからの自然なリンクは、検索順位を大きく押し上げる力を持っています。
しかし、かつてのような自作自演のリンクや、低品質なサイトからのリンク購入は、もはやペナルティの対象となるスパム行為です。現代の被リンク獲得(リンクビルディング)とは、「他者が思わず参照・紹介したくなるような、価値ある存在になる」という、極めて真っ当で、戦略的な広報活動に近いものへと進化しています。
影響力の高い「質の高い被リンク」とは?
まず、どのような被リンクに価値があるのか、その判断基準を理解する必要があります。
- リンク元サイトの権威性:
- 公的機関(.go.jp)、教育機関(.ac.jp): 最も信頼性が高いと見なされます。
- 大手メディア、業界の専門サイト: 広く認知され、専門性が高いサイトからのリンクは価値が高いです。
- AhrefsのDR(ドメインレーティング)などの指標: あくまで参考値ですが、サイト全体の権威性を数値で測るツールも判断材料になります。
- リンク元コンテンツとの関連性:
- 自サイトのテーマと、リンクが張られているページのテーマが、文脈上、密接に関連していることが重要です。
- リンクの自然さ:
- 広告や金銭の授受を目的としたリンクではなく、コンテンツの価値が評価された結果として、編集者や執筆者の判断で自然に設置された「エディトリアルリンク」であることが理想です。
質の高い被リンクを獲得するための実践テクニック
影響力の高い被リンクは、待っているだけでは獲得できません。意図的に、そして戦略的に獲得機会を創出していく必要があります。
- リンクされる「資産」となるコンテンツを作る
これが、全ての被リンク獲得戦略の土台です。他者が引用・参照したくなるような、唯一無二の価値を持つコンテンツを自サイト内に作成します。
- 独自の調査・研究レポート:
- 自社で実施したアンケート調査、市場分析、独自の研究結果などを、グラフやデータを交えて公開します。こうした一次情報は、ニュースメディアやブロガーにとって格好の引用元となり、多くの自然なリンクを生み出す可能性があります。
- 無料の便利ツールやテンプレート:
- ユーザーの特定の課題を解決する、便利なオンラインツール(例:住宅ローンシミュレーター、文字数カウントツール)や、ダウンロード可能なテンプレート(例:事業計画書の雛形、請求書フォーマット)を無料で提供します。その利便性の高さから、多くのサイトで「便利なツール」として紹介され、リンクが集まります。
- インフォグラフィック:
- 複雑な情報や統計データを、視覚的に分かりやすく表現したインフォグラ- 究極のガイド記事(ピラーコンテンツ):
- あるトピックについて、考えられるあらゆる情報を網羅し、体系的にまとめた「決定版」となるガイド記事を作成します。「このテーマについては、この記事を読んでおけば間違いない」という評価を得られれば、多くのサイトから参照元としてリンクされるようになります。
- 戦略的なアウトリーチ(働きかけ)
価値あるコンテンツを作成したら、それが適切な人々の目に触れるように、能動的に働きかけます。
- プレスリリースの配信:
- 前述の独自調査の結果や、新サービスの発表など、ニュース性のある情報をプレスリリースとして配信します。これにより、Webメディアに取り上げられ、記事内で自サイトへのリンクが設置される機会を創出します。
- 言及(サイテーション)のリンク化依頼:
- Web上で、自社の社名やブランド名、あるいはコンテンツが、リンクなしで言及されているケースがあります。こうした言及を見つけ出し(Googleアラートなどで監視)、「この記事で弊社について言及いただきありがとうございます。もしよろしければ、読者の便宜のために、言及箇所から弊社サイトへリンクを張っていただけないでしょうか」と、丁寧にお願い(リンクアーニング)するのも有効な手法です。
- ゲスト投稿(寄稿):
- 自社と関連性の高いテーマを扱う、他のメディアやブログに、専門家として記事を寄稿させてもらう手法です。質の高い記事を提供することで、メディア側にもメリットがあり、記事内の著者プロフィール欄などから自サイトへのリンクを獲得できます。
被リンク獲得は、一朝一夕に成果が出るものではありません。しかし、その本質は、良質なコンテンツを通じて、Webの世界で信頼と評判を築き上げていくプロセスそのものです。この地道な努力こそが、競合が容易には模倣できない、強固な権威性の源泉となるのです。
6. 地域名キーワードを狙うローカルSEOのコツ
飲食店、クリニック、美容室、工務店、士業事務所など、特定の地域で、対面でのサービスを提供する「ローカルビジネス」にとって、最も重要な集客チャネル、それがローカル検索です。ユーザーが「渋谷 ランチ」「横浜 税理士」のように「地域名 + サービス名」で検索した際に、いかにして自社の情報を的確に届け、来店に繋げるか。このローカル検索を制するための施策が「ローカルSEO(MEOとも呼ばれる)」であり、その成功はビジネスの売上に直結します。
ローカルSEOの主戦場「ローカルパック」
ローカル検索の結果画面で、通常のWebサイトのリストよりも上に、地図情報と共に3つのビジネス情報が表示されるエリア。これが「ローカルパック」です。ここは検索結果の最一等地であり、ユーザーの視線を最も集めるため、この3枠の中に表示されることが、ローカルSEOの最大の目標となります。
Googleは、ローカル検索の順位を決定する上で、主に「関連性」「距離」「知名度」の3つの要素を考慮しています。これらの評価を高めるための具体的な施策の中心となるのが、無料で利用できる「Googleビジネスプロフィール(GBP)」の最適化です。
GBP最適化:ローカルSEOの9割はここで決まる
Googleビジネスプロフィールを、単なる「地図上の登録情報」と侮ってはいけません。これは、あなたのビジネスのデジタル上の「店舗」そのものです。この店舗をいかに魅力的に、そして情報豊富に作り込むかが、全てを決定します。
- 基本情報の徹底的な網羅と統一 (関連性UP):
- NAP情報 (Name, Address, Phone): ビジネス名、住所、電話番号は、公式サイトや他のポータルサイトなど、全てのWeb媒体で一字一句違わずに完全に統一します。
- カテゴリ: 自社の事業を最も的確に表すメインカテゴリと、関連する追加カテゴリを複数設定します。
- 属性情報: 「テイクアウト対応」「Wi-Fiあり」「バリアフリー」など、自社に当てはまる属性は全て設定します。これが、ユーザーの細かいニーズに応えるための重要なフィルターとなります。
- 写真と動画で魅力を最大化 (知名度UP):
- 外観、内観、商品・サービス、スタッフの笑顔など、ビジネスの魅力が伝わる高品質な写真を最低でも30枚以上は登録しましょう。写真は多ければ多いほど良いです。ユーザーが投稿した写真も含め、GBPはあなたのビジネスのビジュアルカタログです。
- 口コミ(レビュー)の獲得と管理 (知名度UP):
- 口コミの数、評価の高さ、そして投稿の頻度は、ローカルSEOにおける最重要ランキング要因です。
- 獲得の仕組み化: 来店客に、口コミ投稿をお願いするためのQRコード付きカードを渡すなど、依頼フローを仕組み化しましょう。
- 全件返信の徹底: 投稿された全ての口コミに、24時間以内に、感謝と誠意を込めて丁寧に返信します。特にネガティブな口コミへの真摯な対応は、他の潜在顧客からの信頼を勝ち取る絶好の機会です。
- 投稿機能とQ&Aの活用 (関連性UP):
- 投稿機能: キャンペーン情報、新商品、日々の出来事などを、週に1〜2回のペースで発信し、情報の鮮度を保ちます。
- Q&A: ユーザーからの質問に答えるだけでなく、「よくある質問」を自ら投稿し、回答する「自作自演Q&A」で、顧客の不安を先回りして解消します。
公式サイトで行うローカルSEOのコツ
GBPだけでなく、自社の公式サイト(ホームページ)も、ローカルSEOの評価を高める上で重要な役割を担います。
- 各ページへの地域名キーワードの最適化:
- サイトのtitleタグやh1見出しに、「【地域名】の〇〇なら|会社名」のように、自然な形で地域名キーワードを盛り込みます。
- フッターには、全ページ共通でNAP情報を正確に記載します。
- 地域に特化したコンテンツの作成:
- 「〇〇(地域名)で△△(サービス)を選ぶ際の3つのポイント」
- 「△△(近隣の駅名)からのアクセス方法と周辺情報」
- 「〇〇(地域名)での施工事例・お客様の声」
- といった、地域に根差したテーマのブログ記事やページを作成することで、サイト全体がその地域と強い関連性を持つことをGoogleにアピールできます。
- ローカルなサイテーションの獲得:
- 地域の商工会議所、地方自治体のサイト、地域の情報ポータルサイト、地域の他業種のサイトなど、地域性の高いWebサイトから、NAP情報と共に言及されたり、リンクされたりする(サイテーション)ことは、「知名度」を高める上で非常に有効です。
ローカルSEOは、テクニック以上に、地域社会との繋がりや、顧客一人ひとりとの誠実なコミュニケーションが成果に繋がる、極めて本質的なマーケティング活動です。デジタル上の「店舗」を磨き上げ、地域で最も信頼される存在を目指しましょう。
7. SEOの成果を最大化するA/Bテスト
Webマーケティングの世界において、絶対的な「正解」は存在しません。成功しているように見える施策も、もしかしたら、もっと良いやり方があったのかもしれない。この「もっと良くできるはず」という可能性を探求し、データに基づいて施策の効果を科学的に最大化していくための強力な手法、それが「A/Bテスト」です。
SEOの領域においても、A/Bテストは、クリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)を改善し、最終的なビジネス成果を高めるために、極めて有効なアプローチとなります。
SEOにおけるA/Bテストとは?
A/Bテストとは、ある要素について2つのパターン(AパターンとBパターン)を用意し、ユーザーをランダムに2つのグループに分けて、どちらのパターンがより高い成果(クリックやコンバージョンなど)を生み出すかを、実際のデータに基づいて比較検証する手法です。
例えば、Webサイトのボタンの色を「赤」と「緑」のどちらにした方がクリックされやすいか、といった検証が典型例です。
SEOの文脈におけるA/Bテストでは、主に以下のような要素を対象とします。
- titleタグとmeta description: 検索結果画面でのクリック率(CTR)に最も大きな影響を与える要素。
- ページ内の見出し (h1, h2): ユーザーの興味を引きつけ、読み進めてもらうための導入部分。
- CTA (Call to Action): 「詳しくはこちら」「資料請求」といった、ユーザーの行動を促すボタンやリンクの文言、デザイン。
- コンテンツの構成や順序: ページ内の情報の並び順を変えることで、ユーザーの理解度や満足度がどう変化するか。
なぜSEOにA/Bテストが有効なのか
- クリック率 (CTR) の向上:
- 検索順位が同じでも、クリック率が2%から4%に倍増すれば、サイトへの流入数も2倍になります。titleタグやmeta descriptionは、SEO担当者が直接コントロールでき、かつCTRに大きな影響を与える数少ない要素です。A/Bテストを繰り返すことで、ユーザーの心を最も惹きつける「勝ちパターン」の言葉を見つけ出すことができます。
- コンバージョン率 (CVR) の向上:
- サイトに訪れたユーザーを、いかにして問い合わせや購入といった成果(コンバージョン)に繋げるか。CTAの文言を「資料請求」から「無料ダウンロード」に変えるだけで、CVRが劇的に改善することもあります。A/Bテストは、ユーザー心理の微妙な違いをデータで明らかにし、サイトの収益性を直接的に高めます。
- データに基づいた意思決定:
- 「おそらく、このタイトルの方が良いだろう」といった、主観や憶測に基づいたサイト改善は、失敗のリスクを伴います。A/Bテストは、「AよりもBの方が、CTRが15%高かった」という客観的なデータに基づいて意思決定を行うため、改善の成功確率を飛躍的に高めます。
SEO A/Bテストの実践ステップ
ステップ1:目標と仮説の設定
まず、何を改善したいのか(目標)と、そのための仮説を立てます。
- 目標: 〇〇というページの、オーガニック検索からのクリック率(CTR)を10%向上させる。
- 仮説: 現在のtitleタグは機能的な説明に寄りすぎている。より緊急性や具体的なメリットを訴求する文言に変えることで、ユーザーの興味を引き、CTRが向上するのではないか。
ステップ2:テストパターンの作成
仮説に基づいて、元のパターン(A)と、新しいパターン(B)を作成します。
- A (オリジナル): title: 〇〇(サービス名)の機能と料金プラン|会社名
- B (テストパターン): title: 【今すぐ試せる】〇〇(サービス名)で業務時間を80%削減!|会社名
ステップ3:テストツールの選定と実装
SEOのA/Bテストには、専用のツールが必要です。ページのHTMLを直接書き換えるのではなく、ツール側でユーザーに表示するパターンを振り分け、効果を計測します。
- 代表的なツール:
- VWO (Visual Website Optimizer), Optimizely: 世界的に利用されている高機能なA/Bテストツール(有料)。
- Google Optimize (提供終了): かつては無料で利用できましたが、現在はサービスを終了しています。
- サーバーサイドでの実装: より高度な方法として、自社のサーバー側で表示を振り分ける方法もありますが、専門的な技術知識が必要です。
- 手動でのテスト(擬似A/Bテスト): ツールを使わず、一定期間(例:2週間)ごとにtitleタグを書き換え、GoogleサーチコンソールでCTRの変化を比較する方法もあります。厳密なテストではありませんが、簡易的な検証としては有効です。
ステップ4:テストの実施とデータ収集
ツールを設定し、一定期間(統計的に有意な差が出るまで、最低でも1〜2週間程度)テストを実施し、データを収集します。
ステップ5:結果の分析と勝者の実装
収集したデータを分析し、どちらのパターンが目標指標(この場合はCTR)を有意に改善したかを判断します。もしBパターンが勝者であれば、サイトのHTMLを正式にBパターンの内容に書き換えます。そして、この結果から得られた知見(「うちのユーザーには、緊急性よりも具体的な効果を数字で示す方が響くようだ」)を、次のテストの仮説へと繋げていきます。
A/Bテストは、一度で終わるものではありません。この「仮説→実行→検証→改善」というサイクルを、サイトの重要なページで粘り強く回し続けること。それこそが、競合とのわずかな差を積み重ね、最終的に大きな成果へと繋げる、データドリブンSEOの神髄なのです。
8. ユーザー体験(UX)とSEOの関係性
かつてのSEOは、検索エンジンのロボット(クローラー)をいかに満足させるか、という技術的な側面に重きが置かれていました。しかし、GoogleのアルゴリズムがAIによって人間のようにコンテンツを理解し、ユーザーの行動を分析できるようになった現代において、その様相は一変しました。
今日のSEOにおける成功の鍵は、「検索エンジン」の先にいる「生身のユーザー」をいかに満足させられるか、すなわちユーザー体験(UX:User Experience)の質をいかに高められるかに懸かっています。優れたUXは、もはや単なる「おもてなし」ではなく、検索順位を直接的に左右する、極めて重要なランキング要因なのです。
なぜGoogleはUXを重視するのか
Googleの目的は、ユーザーの検索意図に対して、最高の答えを提供することです。そして、その「最高の答え」とは、単に情報が正しいだけでなく、その情報をストレスなく、快適に、そして満足のいく形で得られる体験全体を指します。
もし、GoogleがUXの低いサイト(表示が遅い、広告が邪魔、スマホで見にくいなど)を上位に表示させてしまったら、ユーザーは「Googleの検索結果は使い物にならない」と感じ、他の検索エンジンに乗り換えてしまうかもしれません。Googleにとって、ユーザーからの信頼を維持し、自社のプラットフォームを使い続けてもらうために、UXの高いサイトを優遇することは、ビジネス上の至上命題なのです。
UXがSEOに与える影響のメカニズム
優れたUXは、以下のようなメカニズムを通じて、SEOにポジティブな影響を与えます。
- 直接的なランキングシグナルとしての評価:
- コアウェブバイタル (Core Web Vitals): Googleは、ページの表示速度 (LCP)、応答性 (INP)、視覚的な安定性 (CLS)を数値化した「コアウェブバイタル」を、検索順位の決定要因として明確に組み込んでいます。これらの指標が良好であることは、優れたUXの技術的な土台であり、直接的なSEO評価に繋がります。
- モバイルフレンドリー: スマートフォンでの閲覧・操作のしやすさは、モバイル検索が主流の現代において、絶対的な評価基準です。
- 間接的なシグナル(ユーザー行動)の改善:
- Googleは、検索結果をクリックした後のユーザーの行動を、「RankBrain」などのAIアルゴリズムを通じて分析していると言われています。優れたUXのサイトは、ユーザー行動に関する指標を改善し、結果として間接的にSEO評価を高めます。
- クリック率 (CTR) の向上: 検索結果画面でのtitleやdescriptionが分かりやすく、魅力的であれば、クリック率は高まります。
- 直帰率の低下・滞在時間の増加: サイトが表示された後、すぐに検索結果に戻ってしまう(直帰)ユーザーが少なく、サイト内を長く回遊してくれる(滞在時間が長い)ことは、「このページはユーザーの期待に応えている」というポジティブなシグナルとなります。
- コンバージョン率 (CVR) の向上: サイトが使いやすく、情報が分かりやすければ、問い合わせや購入といった最終的な成果(コンバージョン)にも繋がりやすくなります。
UXを向上させるための具体的なSEO施策
UXの改善は、Webサイトのあらゆる側面に及びます。
- ナビゲーションの最適化:
- ユーザーが「今、サイトのどこにいるのか」「探している情報はどこにあるのか」を、直感的に理解できるような、分かりやすいメニュー構造(グローバルナビゲーション)や、パンくずリストを設計します。
- サイト内検索の強化:
- 特に情報量が多いサイトでは、ユーザーが目的の情報をすぐに見つけられるように、高性能なサイト内検索機能を提供することが重要です。検索窓は目立つ場所に配置し、入力候補の表示(サジェスト)や、多少の入力ミスを補正する機能があると、さらにUXは向上します。
- コンテンツの可読性向上:
- 適切な文字サイズと行間、見出しや箇条書きによる情報の構造化、図解や画像の活用など、ユーザーがストレスなく内容を読み進められるように、コンテンツの見た目を整えます。
- 煩わしい要素の排除:
- コンテンツを覆い隠すような intrusiveなポップアップ広告や、自動再生される動画など、ユーザーの閲覧を妨げる要素は、UXを著しく損ない、Googleからの評価を下げる原因にもなります。
SEOとUXは、もはや切り離して考えることはできません。「ユーザーにとって最高の体験は何か?」という問いを常に中心に据え、技術的な改善とコンテンツの質の向上を両輪で進めていくこと。それこそが、Googleとユーザーの両方から愛され、長期的に成功し続けるWebサイトを築くための、唯一の道なのです。
9. AIによるコンテンツ生成とSEOの行方
2023年以降、ChatGPTに代表される生成AI(Generative AI)の技術が爆発的に進化し、Webマーケティングの世界に、かつてないほどの大きなインパクトを与えています。特に、コンテンツ制作の領域において、AIはもはや無視できない存在となりました。このAIによるコンテンツ生成は、SEOの世界にどのような変化をもたらし、私たちはその未来にどう向き合っていくべきなのでしょうか。
Googleの公式見解:AIコンテンツは悪ではない
まず理解しておくべき最も重要な点は、Googleの公式なスタンスです。Googleは、「AIによって生成されたかどうか」という、コンテンツの作成方法自体を問題視しているわけではありません。Googleが一貫して問題視しているのは、「ユーザーのためではなく、検索順位を操作することだけを目的として作られた、低品質なスパムコンテンツ」です。
Googleの検索セントラルブログでは、「AIの活用いかんにかかわらず、高品質なコンテンツを評価する」と明言されています。つまり、たとえAIが生成したコンテンツであっても、それがE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の基準を満たし、ユーザーにとって有益で、オリジナルな価値を提供するものであれば、何ら問題はなく、むしろ評価の対象となり得るのです。
逆に、人間が書いたコンテンツであっても、他のサイトから情報をコピー&ペーストしただけのような、低品質なものであれば、評価されないのは当然です。
AIがSEOにもたらす「機会」と「脅威」
AIによるコンテンツ生成は、SEO担当者にとって、大きな「機会」と「脅威」の両側面を持っています。
【機会:生産性の飛躍的向上】
- コンテンツ制作の効率化:
- これまで多くの時間を要していた、記事の構成案(骨子)の作成、リサーチ、文章の草稿作成といった作業を、AIは驚異的なスピードで補助してくれます。これにより、マーケターは、より戦略的な思考や、クリエイティブな企画といった、人間にしかできない、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
- アイデアの壁打ち相手:
- 新しいコンテンツの切り口や、キャッチーなタイトルのアイデア出しに詰まった時、AIは無限のブレインストーミングパートナーとなってくれます。
【脅威:コンテンツの均質化とコモディティ化】
- 没個性なコンテンツの氾濫:
- 誰でも簡単に、それなりの品質の記事が生成できるようになった結果、Web上には、どこかで見たような、似たり寄ったりの、没個性なコンテンツが溢れかえることが予想されます。AIが生成する文章は、インターネット上の膨大な既存データを学習しているため、どうしても平均的で、当たり障りのない内容になりがちです。
- E-E-A-T、特に「経験(Experience)」の欠如:
- AIは、実際に製品を使用した経験や、現地を訪れた体験を持っていません。そのため、AIが生成しただけのコンテンツは、Googleが近年ますます重視している「E-E-A-T」、特に「E(経験)」の基準を満たすことができません。一次情報に基づかない、深みのないコンテンツは、いずれ淘汰されていくでしょう。
AI時代のSEOで生き残るためのコンテンツ戦略
AIの脅威を乗り越え、機会を最大限に活かすためには、コンテンツ戦略の考え方をアップデートする必要があります。
- AIは「アシスタント」、人間は「編集長」
AIに100%の執筆を任せ、生成された文章をそのまま公開するのは、最も危険な行為です。これからのコンテンツ制作は、AIと人間の「協業」が基本となります。
- AIの役割: リサーチ、構成案作成、下書き、文章の校正・リライト
- 人間の役割:
- 企画・戦略: 誰の、どんな課題を解決するためのコンテンツなのか、その目的と戦略を定義する。
- 独自価値の付与: AIが生成した下書きに、自社ならではの経験、独自のデータ、専門家としての個人的な見解、顧客の生の声といった、「血の通った一次情報」を注入し、編集・追記する。
- ファクトチェックと品質保証: AIが生成した情報に、事実誤認や偏見がないかを厳しくチェックし、コンテンツ全体の品質に最終的な責任を持つ。
- 「経験」と「人間性」で差別化する
AIが生成した均質的なコンテンツとの差別化を図る、最も強力な武器。それが、E-E-A-T、特に「経験」と、それに基づく「人間性」です。
- 著者情報を前面に押し出す: 「誰が」この情報を発信しているのか、著者の顔、経歴、そしてその分野にかける想いを明確に示し、コンテンツに「人としての体温」を与える。
- ストーリーテリング: 成功体験だけでなく、失敗談や試行錯誤のプロセスといった、生々しいストーリーを語ることで、読者の共感を呼び、AIには模倣できない深みを生み出します。
- コミュニティとの対話: コメントやSNSを通じて、読者と対話し、そこから得られたフィードバックをコンテンツに反映させていく。
AIの進化は、私たちに「人間にしか提供できない価値とは何か?」という、本質的な問いを突きつけています。AIを賢く活用し、生産性を高めつつ、最終的には人間ならではの経験と創造性で勝負する。それこそが、AI時代のSEOの行方を左右する、唯一の羅針盤となるのです。
10. SEOの成功事例から学ぶ効果的な戦略
SEOの理論やテクニックを学ぶことは重要ですが、それらが実際のビジネスの現場で、どのように組み合わされ、どのような成果に繋がったのか、具体的な「成功事例」から学ぶことは、自社の戦略を磨き上げる上で、何物にも代えがたいヒントを与えてくれます。ここでは、異なるビジネスモデルにおけるSEOの成功事例を分析し、その背後にある共通の効果的な戦略を抽出します。
事例1:BtoB(製造業)におけるコンテンツマーケティングの成功
- 企業: ある特殊な部品を製造する中小企業。
- 課題 (Before):
- 製品の専門性が高く、従来の展示会や代理店経由の営業では、新規の顧客(設計・開発担当者)に効率的にリーチできていなかった。
- Webサイトは存在するものの、製品カタログのような情報しかなく、問い合わせは月に数件程度だった。
- 戦略・施策 (Action):
- ペルソナ設定とキーワード調査: ターゲットとなる設計・開発担当者が、どのような技術的な課題を抱え、どのような専門用語で検索するかを徹底的に調査。「〇〇(技術名) 原理」「△△(課題) 解決方法」といった、課題解決型のキーワードを多数発掘。
- 技術ブログ(オウンドメディア)の立ち上げ: 発掘したキーワードに対する「答え」となる、専門的で質の高い技術解説記事を、社内の技術者が執筆・監修する形で、週に1本のペースで公開。単なる製品紹介ではなく、技術の原理原則や、設計上の注意点といった、読者(潜在顧客)に純粋に役立つ情報を提供することに徹した。
- ホワイトペーパー(お役立ち資料)の作成: ブログ記事で興味を持った読者に対して、「より詳細な技術資料」や「設計ガイドブック」を、ホワイトペーパーとして無料でダウンロードできるように設置。ダウンロード時に、会社名や連絡先などのリード情報を獲得する仕組みを構築。
- 成果 (After):
- 1年後、技術ブログは月間数万PVを集めるメディアに成長。
- 様々な技術キーワードで検索上位を独占し、これまで接点のなかった大手企業の開発担当者からも、Webサイト経由での問い合わせが月間50件以上安定的に入るように。
- 獲得したリードに対して、営業が的確なアプローチをすることで、成約率が従来の3倍に向上。
- 学ぶべきポイント:
- 「売り込み」ではなく「価値提供」に徹する: 専門知識を惜しみなく提供することで、専門家としての信頼を勝ち取り、自然と見込み客が集まる仕組みを構築した。
- E-E-A-Tの体現: 社内の技術者が持つ、他社にはない専門知識(Expertise)と実務経験(Experience)をコンテンツ化し、競合との圧倒的な差別化に成功した。
事例2:地域密着型(クリニック)におけるローカルSEOの成功
- 企業: 地方都市で新規開業した、ある専門分野に特化したクリニック。
- 課題 (Before):
- 新規開業のため、地域での知名度が全くない。
- 近隣には、長年の実績を持つ競合クリニックが複数存在する。
- 広告にかけられる予算は限られている。
- 戦略・施策 (Action):
- Googleビジネスプロフィール(GBP)の徹底的な最適化: 開業前に、GBPの情報を100%入力。特に、クリニックの専門性が伝わる詳細なサービス内容や、院内の清潔感・安心感が伝わる写真を豊富に掲載。
- 口コミ獲得の仕組み化: 開院当初から、来院した患者一人ひとりに対して、診察後の満足度が高いタイミングで、院長自らが「もしよろしければ、Googleマップでの評価にご協力いただけますか」と、口コミ投稿をお願いすることを徹底。QRコード付きのカードも配布。
- 全ての口コミへの真摯な返信: 投稿された全ての口コミに対して、院長が24時間以内に、感謝や共感を示すパーソナルなコメントを返信。
- 地域+お悩みキーワードでのブログ発信: 「〇〇市 △△(症状) 原因」「□□(近隣駅名) 〇〇治療」といった、地域の患者が抱える具体的な悩みに応えるブログ記事を、公式サイトで定期的に発信。
- 成果 (After):
- 半年後、「地域名 + 専門分野」のキーワードで、競合を抑えてローカルパックの1位に表示されるように。
- 質の高いポジティブな口コミが100件以上蓄積され、それが強力な来院動機に。
- 広告費をほとんどかけずに、新規患者の8割以上がWeb(Googleマップ・検索)経由となり、開業1年で地域の人気クリニックとしての地位を確立。
- 学ぶべきポイント:
- ローカルSEOへの一点集中: 限られたリソースを、最も費用対効果の高いロー- 口コミというUGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用: 顧客(患者)を巻き込み、信頼の輪を広げていく戦略が、競合との最大の差別化要因となった。
これらの事例に共通するのは、小手先のテクニックに頼るのではなく、自社の強みを定義し、ターゲット顧客の課題に真摯に向き合い、価値を提供し続けるという、極めて王道のアプローチです。自社のビジネスモデルに合った成功事例を参考に、その背後にある戦略的思考を自社のものとすること。それが、SEOを成功に導くための、最も確実な近道なのです。
まとめ
本稿では、2025年以降の最新の検索環境を前提に、SEOで検索上位を独占し、ビジネスの集客力を飛躍的に高めるための、実践的なノウハウを網羅的に解説してきました。その根底に流れるのは、もはやGoogleのアルゴリズムを欺くようなテクニックではなく、「いかにして、検索ユーザーという”人間”の、複雑で多様なニーズに、最高の形で応えるか」という、極めて本質的な問いです。
顧客が検索するキーワードとその意図を深く洞察し、競合が提供できていない価値を、E-E-A-Tを体現する独自のコンテンツで提供する。そして、そのコンテンツが正しく評価されるための技術的な土台を整え、第三者からの信頼の証である被リンクを獲得していく。これらの施策は全て、ユーザーファーストという一点に収斂されます。
A/Bテストでユーザーの反応を科学的に検証し、UX(ユーザー体験)を向上させ、AIという新たなテクノロジーを賢く活用する。これらのアプローチもまた、ユーザーへの提供価値を最大化するための手段に他なりません。
SEOは、一度設定すれば終わりという魔法の杖ではありません。それは、市場と対話し、顧客と向き合い、自社の価値を問い続ける、終わりなき改善のプロセスです。しかし、その地道な努力の先にこそ、広告費に依存しない、持続的で強固な集客基盤の構築と、ビジネスの揺るぎない成長が待っています。本稿で得た知識とノウハウを羅針盤として、あなたのビジネスを、検索エンジンと顧客の両方から選ばれる、唯一無二の存在へと導いてください。

執筆者
畔栁 洋志
株式会社TROBZ 代表取締役
愛知県岡崎市出身。大学卒業後、タイ・バンコクに渡り日本人学校で3年間従事。帰国後はデジタルマーケティングのベンチャー企業に参画し、新規部署の立ち上げや事業開発に携わる。2024年に株式会社TROBZを創業しLocina MEOやフォーカスSEOをリリース。SEO検定1級保有
NEXT
SERVICE
サービス