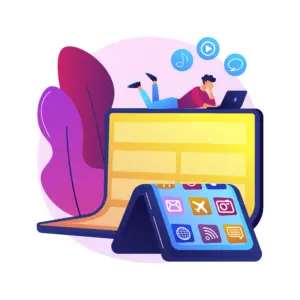ナレッジハブ
2025/4/26
検索エンジンに評価されるコンテンツの作り方とは?
目次
SEOに強い記事の共通点は「意図」と「信頼性」への深い理解にある
検索エンジンで上位表示されるコンテンツには、共通する要素がいくつかあります。ただ単に文字数が多ければ良い、キーワードを詰め込めば良いという時代はすでに終わっています。現在のGoogleは、検索ユーザーの意図に合致しているか、情報に信頼性や独自性があるか、そして技術的に正しく構造化されているかといった複合的な要素でコンテンツを評価しています。
特に注目すべきなのは「検索意図への最適化」です。ユーザーがどのような疑問や課題を持ってそのキーワードで検索しているのかを読み取り、それに対して適切な情報を提供することが、SEOにおいて最も重要な戦略となっています。たとえば「WordPress SEO 対策」と検索する人は、具体的な設定方法やプラグインの紹介を求めている可能性が高く、それに対して概要だけを書いても上位には表示されません。
また、Googleが提唱するE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)も、コンテンツ制作において意識すべき評価基準です。特にYMYL(Your Money or Your Life)領域に該当するテーマ、たとえば医療、法律、金融などに関しては、この評価軸がより厳しく適用され、専門家の監修や出典の明示が重要視されます。
構造的な面では、見出しタグ(H2〜H4)の適切な使用、読みやすい段落分け、内部リンクの配置、構造化データの実装なども、検索エンジンが内容を理解する上での補助要素として機能します。さらに、画像の最適化やalt属性の活用、ページ表示速度の高速化など、テクニカルなSEO要素も無視できません。
さらに、公開したコンテンツをそのまま放置するのではなく、アクセス解析や検索順位を元にリライトを行うことで、情報の鮮度と価値を維持することができ、Googleからの評価も向上します。これは“運用型SEO”とも言えるアプローチで、継続的に改善することが重要です。
本記事では、「検索に強い記事とはどのような構成で、どのように書くべきか」をテーマに、SEOで成果を出すための具体的な戦略を5つのセクションに分けて解説していきます。初心者から中上級者まで、実践に役立つ内容としてご活用ください。
1. 検索意図に合ったコンテンツ作成のコツ
検索エンジンに評価されるコンテンツを作るための第一歩は、「検索意図を正確に読み解くこと」です。検索意図とは、ユーザーが特定のキーワードで検索した際に、どのような情報を求めているのかという“裏にあるニーズ”のことを指します。たとえば、「SEO 初心者」と検索するユーザーは、専門的なアルゴリズムの解説ではなく、まずは用語や概要、基本的な対策方法を知りたいと考えている可能性が高いです。
検索意図には、主に3つのタイプが存在します。情報収集型(Knowクエリ)、比較検討型(Doクエリ)、購入意図型(Buyクエリ)です。ユーザーがどの段階にいるかを把握し、それに合わせた構成と情報量でコンテンツを提供することで、離脱率を下げ、滞在時間を延ばすことができます。
Googleは近年、BERTやMUMといった自然言語処理アルゴリズムを導入し、検索クエリの文脈理解力を大幅に高めています。つまり、キーワードが一致しているだけではなく、「この文章はユーザーの意図に応えているか」をコンテンツ全体の流れや構成から読み取って評価するようになってきています。そのため、単なるキーワードの羅列ではなく、ユーザーの思考フローに寄り添ったコンテンツ設計が重要です。
検索意図を的確に捉えるためには、まずGoogle検索でキーワードを打ち込み、実際に表示されている上位10件のページを分析することが有効です。そこにはGoogleが「検索意図に合っている」と判断したコンテンツが表示されているため、どのような形式(例:Q&A形式、手順形式、リスト型など)で書かれているのか、どんなトピックが盛り込まれているのかを確認できます。
また、「関連キーワード」や「People also ask(他の人はこちらも質問)」なども検索意図のヒントとなります。たとえば、「SEO 対策 方法」というキーワードで検索すると、「SEO対策には何をすればいい?」「無料でできる方法は?」といった質問形式の候補が出てくることがあり、これらを見出しに取り入れて回答する形で構成すると、検索意図との一致率が高まります。
さらに、Google Search Consoleのデータを使って、既存コンテンツに流入しているキーワードとクリック率、掲載順位を分析することで、狙った検索意図にどれだけマッチしているかを確認できます。もし表示回数は多いのにクリックされていない場合、それはタイトルやディスクリプションが意図を的確に表現できていない証拠かもしれません。
検索意図に寄り添ったコンテンツとは、ユーザーが検索する前に持っていた疑問に対して「自分のために書かれている」と思わせる内容であるべきです。この“読者の共感”を得る構成こそが、検索エンジンに評価されるだけでなく、ユーザーの満足度を高める最大の秘訣です。
2. オリジナル性と権威性を高める記事の書き方
検索エンジンは、オリジナル性と権威性を兼ね備えたコンテンツを高く評価します。とくにGoogleは、同一ジャンルの情報が大量に出回る中で「どれだけ独自の価値を提供できているか」を重視する傾向が強まっています。つまり、他サイトの情報をまとめただけでは上位表示は難しく、読者に新しい気づきや深い理解をもたらす視点が必要不可欠です。
オリジナル性を高めるには、まず“経験”をコンテンツに織り込むことが効果的です。たとえば、同じ「SEO対策」というテーマであっても、「実際に検索順位が上がった施策事例」や「失敗から学んだ教訓」など、執筆者の体験に基づいた内容は、それ自体が唯一無二の情報となり、他の記事と明確な差別化を生み出します。
Googleの検索品質評価ガイドラインでも、「E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)」という評価基準が明記されています。E(Experience:経験)を新たに追加したことからも、単なる理論だけでなく、実体験に裏打ちされた情報の価値が重視されていることがわかります。
さらに、引用元や出典を明示することも権威性を高めるためには重要です。信頼できる統計データや公式資料を用い、それを元に解釈や分析を加えることで、説得力が格段に上がります。出典は可能な限り一次情報(政府機関、大学、企業の公式レポートなど)を使用することが望ましく、情報の正確性や客観性も高めることができます。
また、専門的な内容を扱う際には、著者のプロフィールや専門資格、実績などを記事内またはプロフィールページに明示しておくと、Googleに対して「この情報は信頼できる人物から発信されている」と示す効果があります。特に医療、法律、金融といったYMYL領域ではこの信頼性がSEO評価に直結します。
読みやすさの観点でも、オリジナル性と権威性は両立させる必要があります。専門性の高いテーマであっても、難解な用語や長すぎる文は読者の離脱を招きます。そのため、専門用語には丁寧な解説を加えたり、図表を用いて視覚的な理解を促す工夫が効果的です。
記事の最後には、筆者のまとめや考察、実践のアドバイスなどを加えることで、単なる情報提供から「読者の行動を後押しするコンテンツ」へと昇華させることができます。これにより、ユーザーからの信頼を得られるだけでなく、SNSでのシェアや被リンクにもつながる可能性が高まります。
権威性とオリジナル性は、検索エンジンだけでなく読者にとっても「このサイトなら信頼できる」「また見に来たい」と思わせる最大の要因です。一次情報の活用、自分の言葉での説明、体験に基づく考察——これらを積み重ねることで、唯一無二のコンテンツを生み出すことが可能になります。

3. 内部SEOで重要な構造化データとは?
内部SEOの中でも、検索エンジンにページ内容を正確に理解してもらうために欠かせないのが「構造化データ(Structured Data)」です。構造化データとは、HTMLコードに特別なマークアップを追加して、ページの内容を検索エンジンに伝える仕組みのことを指します。これにより、通常の検索結果よりも視覚的に目立つ「リッチリザルト」が表示され、クリック率の向上や検索評価の強化が期待できます。
たとえば、レシピページに構造化データを追加すると、「調理時間」「カロリー」「評価(星マーク)」といった情報が検索結果に表示されるようになります。これがユーザーの注意を引きやすくなり、他の検索結果との差別化に直結するのです。実際に、Googleの公式発表では、リッチリザルトが表示された場合のクリック率は最大30%増加するというデータも報告されています。
構造化データの記述には「Schema.org」という標準仕様が使われており、Google、Bing、Yahoo、Yandexなどの主要な検索エンジンが共通で採用しています。Schema.orgの語彙には、記事、商品、レビュー、FAQ、イベント、医療情報など数百種類のタイプが用意されており、対象コンテンツに応じて適切なマークアップを選ぶ必要があります。
たとえば、FAQページの場合はFAQPage構造を使い、各質問にはQuestion、回答にはAnswerというタグを付けます。こうすることで、検索結果に「よくある質問」が折りたたみ表示され、ユーザーがクリックする前から内容の一部を把握できるようになります。
また、構造化データはSEOにおける間接的な評価にも影響します。Googleは構造化データをもとにナレッジパネルや検索補助機能(例:パンくずリスト表示、レビュー星の表示など)を充実させており、ユーザーの検索体験の向上に直結しています。これが結果的にサイトへの信頼性や認知度向上にもつながり、検索アルゴリズム上の評価要因としても作用します。
導入の際は、Googleの「構造化データテストツール」や「リッチリザルトテスト」を活用し、マークアップが正しく記述されているか、検索結果にどのように反映されるかを確認できます。WordPressなどのCMSを使用している場合は、構造化データを自動で出力するテーマやプラグイン(例:Yoast SEO、All in One SEOなど)も利用可能です。
構造化データは、直接的な順位上昇をもたらす施策ではないものの、クリック率の向上やユーザーエンゲージメントの改善といった、SEO全体の強化において非常に有効な要素です。検索結果で埋もれず、他のサイトと明確な差をつけるために、今すぐ取り入れるべき内部施策の一つと言えるでしょう。
4. 効果的な画像SEOとalt属性の使い方
SEO対策というと、テキストコンテンツやリンク施策に注目が集まりがちですが、画像もまた検索エンジンにとって重要な評価対象です。特にGoogleは画像検索結果にもユーザーを誘導するアルゴリズムを導入しており、画像SEOをしっかり行うことで、検索流入のチャネルを広げることが可能になります。
画像SEOの第一歩は、「適切な画像形式とサイズの選定」です。画像が重すぎるとページの表示速度が遅くなり、ユーザー体験が悪化します。Googleは表示速度をランキング要因の一つとしており、特にモバイルユーザーに対しては厳格です。画像は基本的にJPEGやWebP形式を使い、圧縮率を調整しながら100KB以内に抑えるのが理想とされています。また、複数の画面サイズに最適化するために、srcsetを活用したレスポンシブ画像の設計も重要です。
次に、画像ファイル名にもキーワードを含めることが推奨されます。たとえば、「img123.jpg」ではなく、「seo-kiso-setsumei.jpg」のように、画像の内容を表すファイル名にすることで、検索エンジンが画像を正確に理解しやすくなります。これは画像検索だけでなく、通常のウェブ検索においてもコンテンツとの関連性を高める一助となります。
さらに見落とされがちなのが「alt属性」の設定です。alt属性とは、画像が表示されない場合に代替テキストとして表示されるもので、視覚障害のあるユーザーがスクリーンリーダーを通して内容を把握する際にも使用されます。Googleはこのalt属性のテキストを重要な指標として利用しており、SEO評価にも直結します。具体的には、「記事内容を補足する説明」や「画像が伝えたい情報」を簡潔に表現することがポイントです。
たとえば、「SEOセミナーの様子を写した写真」であれば、alt属性には「2024年開催のSEOセミナーでの講演風景」などと記述するのが適切です。画像の内容を端的に、かつ自然な文体で記述することが、検索エンジンとユーザー双方にとってわかりやすい説明になります。
画像キャプションの活用も有効です。alt属性と異なり、キャプションはユーザーに直接表示されるため、テキストの補足や訴求ポイントの強調に役立ちます。Googleはキャプションもコンテンツの一部として評価しており、適切な説明があるとコンテンツ全体の質が高いと判断される可能性が上がります。
また、画像をオリジナルで用意することもSEOには大きな利点があります。ストックフォトばかりを使用しているサイトは、画像の独自性が薄く、差別化が難しくなります。実際に、Googleのジョン・ミューラー氏も「独自の画像はSEO上有利」と明言しており、オリジナル画像が検索順位に好影響を与えることは事実です。
画像SEOはテクニカルな側面が多く見えますが、要は「検索エンジンとユーザーにとってわかりやすく、快適に使える画像設計」を意識することが重要です。見た目の美しさだけでなく、裏側の構造にもしっかりと気を配ることが、SEOに強いサイトを構築する鍵となります。
5. 定期的なコンテンツリライトの必要性
SEO対策において、コンテンツを一度作成しただけで終わらせてしまうのは極めて非効率です。検索エンジンは情報の「鮮度」を評価項目の一つとしており、古い情報や時代に合っていない表現は検索順位を落とす原因となります。これを防ぐために有効なのが「定期的なコンテンツのリライト(加筆・修正)」です。
リライトの目的は、情報のアップデートだけに留まりません。検索意図の変化に対応し、キーワードの最適化を行い、ユーザーのニーズにより適した内容へと改善することで、検索エンジンからの評価を維持・向上させることができます。実際に、SEO施策においてリライトは新規コンテンツ作成よりもROIが高い施策とされており、限られたリソースの中で効果を最大化する上でも重要な戦略です。
リライト対象を見極めるには、まずGoogle Search Consoleで既存ページのパフォーマンスを確認します。表示回数が多いのにクリック率が低いページは、タイトルやディスクリプションが検索意図とマッチしていない可能性があります。また、以前は上位に表示されていたのに順位が下がってきているページは、情報の鮮度不足や競合ページの質の向上が原因かもしれません。
リライトの方法としては、まず最新の情報への差し替え、統計データの更新、新たな事例の追加が基本です。加えて、H2〜H4の見出し構成を見直し、論理的な流れになっているか、ユーザーが必要な情報にたどり着きやすいかを再確認します。また、内部リンクや画像の見直し、キーワードの最適化(不自然な詰め込みの排除、関連語の追加)も合わせて実施すると効果的です。
さらに、ユーザーの行動データを参考にすることで、改善ポイントがより明確になります。たとえば、直帰率が高いページは、ファーストビューに重要な情報がない、読みづらい、期待と異なる内容が記載されているなどの問題を抱えている可能性があります。これらを視覚的にもテキスト的にも修正することで、ユーザー体験が改善され、再評価につながります。
リライトを継続するためには、全記事を一括で見直すのではなく、重要ページや流入の多いページから優先順位を付けて進めていくのが現実的です。毎月5〜10本ずつ見直すといった運用体制を整えることで、サイト全体のクオリティを継続的に高めていくことができます。
情報が変化する時代において、コンテンツも“メンテナンスされるべき資産”と捉えることが求められています。リライトは、その資産価値を維持・向上させるための投資であり、SEOの成果を持続させるために欠かせない要素です。
検索に強いコンテンツは、技術と信頼の両立で生まれる
検索エンジンに評価されるコンテンツを作るためには、ただキーワードを入れるだけの施策では通用しません。ユーザーの検索意図を理解し、オリジナリティと専門性を盛り込み、構造的にも整った記事を作ることが求められます。また、構造化データや画像SEOといった技術的な要素も忘れてはならず、リライトによる鮮度維持も中長期的な集客に直結します。
SEOで成果を出すためには、「ユーザーに役立つかどうか」という視点と、「検索エンジンに正しく伝える技術」が両立していることが不可欠です。つまり、検索に強いコンテンツとは、価値と構造のバランスがとれた“設計された情報”であるということです。
本記事で紹介した5つの要素を自社のコンテンツ制作に取り入れ、日々改善を積み重ねることで、自然検索からの流入を着実に増やし、競合との差を広げることが可能になります。コンテンツは一度作って終わりではなく、“育てる”ことが成功への鍵となります。

執筆者
畔栁 洋志
株式会社TROBZ 代表取締役
愛知県岡崎市出身。大学卒業後、タイ・バンコクに渡り日本人学校で3年間従事。帰国後はデジタルマーケティングのベンチャー企業に参画し、新規部署の立ち上げや事業開発に携わる。2024年に株式会社TROBZを創業しLocina MEOやフォーカスSEOをリリース。SEO検定1級保有
NEXT
SERVICE
サービス